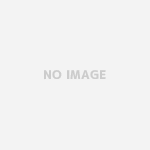おせちメーカーとして約半世紀の歴史を刻む、恵那銀の森。創業者・
渡邉大作の夢「森と共生したい」という強い想いからゴルフ場跡地を買い
取り、この跡地を森に還す森づくり事業を2020年にスタートさせました。
このブログでは、この事業を担う、私たち「3代目森の番人」2名の夢と希望、
ワクワクだけでなく、苦悩やつぶやきもお伝えしたいと思います。
今回は、新工場での芝生管理と、その難しさについて、
お話させてください。

私たちが森をつくる計画を立てているのは、新たにつくられた、
おせち工場周辺。また私たちは、森づくりだけに留まらず、
新工場周辺の芝生管理を森の番人の先輩方に教わりつつ、
担っています。
ちなみにこの写真は、昨年冬のもの。
まだまだ成長していないコウライシバの赤ちゃんたちが、
来春の準備をしているときです。

そして、少し芝が伸びた今年の春。貼りたての芝に、まず
薬剤散布を行ないました。
その内容はというと…
芝生を傷めずに雑草だけに効くもの
芝の根や葉を食べる虫やキノコを防除する殺虫・殺菌剤
芝の刈りカス(サッチと呼ばれます)を分解するもの
芝の栄養となる鉄分
さまざまな効能をもつクスリをブレンドし、芝に与えます。
今春の散布後、雑草の姿はほとんどなく、芝生もスクスク。
このままでも、青々とした芝生ができるのでは。
そんな風に思っていました。

ところが、今年夏。気づけば、そこここに雑草、雑草、雑草…。
特に根っこの強いチガヤの仲間や、花がつくと爆発的に増える
コニシキソウなどなど、強敵がそろい踏み!これには驚きました。
「圃場で育った芝に雑草の種が入っている」とは
聞いていたものの、これほどまでとは…!
特に今年は雨が多いため、どこの芝生にも雑草が繁茂するほか、
芝生そのものも成長しすぎる傾向にあるそうです。

さらに、病気も見つかりました。芝生の専門業者さんの解説によって、
「ラージパッチ」と呼ばれるものや、街灯の下に集まり繁殖する
「ヨトウガ」の仲間など、かなりの影響が出ていることも
わかってきました。
これは対処療法しかないそうで、秋の薬剤にこうした対策用の薬を
いただけるとのこと。25年間にわたり芝生を見てきた同専門業者さんも、
「いまだに芝は良くわからない」というほど、芝生の管理は奥が深いようです。

春秋は刈って肥料を撒いてを繰り返し、横に横にと茎(ランナー)を
伸ばすよう成長させる。夏は肥料を撒かず、休眠する芝を見守って
散水タイミングを図る。そして、春は砂を散布して「床上げ」し、
茎を切らない土壌基礎をつくっていく。病気になりやすいエリアや、
肥料の利きが悪いエリアなど“個性”を読み取り、カラダで覚えていく…。
いつか、森に来られた方々がゆっくりと憩える芝生ができたらとは
思っていましたが、その夢を叶えるにはかなりのノウハウ蓄積が
必要なことがわかってきました。
現状のスキルではあまりに遠い道のりですが、少しずつ、少しずつ、
二代目森の番人がつくる芝(上写真)に近づき、気持ち良く
皆さんをお迎えできるようにしていけたらと思います。
恵那銀の森は、人と森が共生できる社会を目指し、人と森をつなぐ場所づくりの
ひとつとして、閉鎖されたゴルフ場を人が集える場所にしていく「森づくり事業」
を進めています。 いつの日が子どもの笑顔があふれ、人々が森の癒しを感じて
もらえる森ができる日まで。私たちの取り組みは続いていきます。
http://ginnomori.info/shisetsu/ginnomori_vision.htm